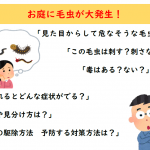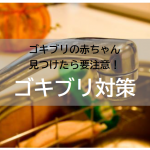- 0800-919-6866年中無休 9:00-18:00
- 無料見積もりはこちら
なぜ鳩は逃げない?人間になれてしまったハト
平和の象徴とも言われているハトですが、日本では、駅や公園・神社やテーマパークなど、比較的人の多い場所で見かけることが多い印象があります。
人への警戒心も少なく餌を探し歩いている可愛らしいイメージがありますが、公共施設や家屋で様々な影響をもたらしているのをご存じでしょうか。
今回は、私たちの身近な場所にいる鳩(ハト)の習性や被害の事例をご紹介していきます。人馴れしたハトへの対策をチェックしてみましょう。
目次
なぜ鳩は逃げない?人馴れしたハト
環境によってだいぶ人馴れした鳩は、人間は餌をくれるもの…と認識してしまっているようです。
カラスほど雑食ではないので公園のゴミ箱を荒らすことはあまりしませんが、私たち人間が良かれとして餌を与えたり、食べモノの捨て方などが原因で寄り付くようになり、人間に馴れてしまいました。
街中にいる鳩は、ハト本来の食生活も乱れ、人間が食するものを覚えてしまったといえます。
人間とハトの歴史はとても長い!
ハトの歴史を辿ると、約10000年前の新石器時代から飼育されていたと言います。
人里に近い場所で営巣し、崖や洞窟などから後に初期人間の住居に巣を作り、生活していたと言われています。
古代から通信用の伝書鳩としてハトの特殊な太陽コンパスと体内時計や地磁石などによって人に活用されてきました。その後、電話通信技術の進歩により、かつてのように活用価値が低下し後に鳩レースが盛んになったとされています。
人々によって飼育方法が異なり、様々な理由のなかで人から離れ野生化したハトが増えていったとされています。

ハトの繁殖を減らすには?
ハトは生まれて1カ月程度で巣立ち、5~6カ月頃に発情し繁殖期に入ります。
通常ハトの繁殖は1年に3~4回ですが産卵期は春頃から秋にかけて産卵します。現在では倍の数の繁殖を行う個体が急増。
長い歴史の人間とハトとの繋がりを学ぶと、現代人の私たちに警戒心なく寄ってくるハトと共同空間で生きているのは古きに渡って同様なのかもしれません。
しかし、どんどん進化していく現代社会の中で、増殖したハトだけではなく、野生の鳥たちが本来の生息場所を失い、便利で餌の豊富な環境があることで人間へ被害を与えてしまっているのは確かです。
ハトが自然の生態系の中で食物を食べて生活するし生息していけるように少しでも人間界での生息を阻止できるような対策が必要です。現代に生きる私たちが、鳩や鳥の環境づくりを考えていかなければならないと言えるでしょう。
公園などにいるハトを追い払う方法は?
居心地の良い餌場となる環境がある以上、慣れ親しんだハトがその場を離れることはとても難しいことです。人がハトの群れを追いかけるよう走っても、驚いてその場を逃げるように羽を広げ移動しますがそう単純なものではありません。
人懐っこいとされるハトが年々増加しているのは、逆に餌を与えてしまっている人間が増加していることが原因にもなります。工業施設や大幅な屋外での追出しはとても困難であり、非常に難しい問題です。
日本の保護法で守られている鳥は、日本の空で何千羽も飼っているということになります。追い払うだけではあまり効果がないことを踏まえ、近づいてこない対策を重点に考える必要があります。そのためのサポートとして、私たちのような害鳥駆除のお仕事が増えています。
勝手に捕まえちゃダメ?
野生の鳩や野鳥は、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲・殺傷・駆除・卵を処分すること飼うことも禁じられています。
私たちのような専門の業者においても同様です。
日本では「鳥獣保護法」という日本国内の鳥獣の保護、狩猟の適正化に関する法律が定められています。これを破ってしまうと「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられます。
保護法を活かし、ここまでハトが増えてしまった原因をあらため直す必要があると言えます。ハトに餌を与えない、ゴミの捨て方など、一人ひとりのマナー意識でハトの被害を防ぐことができるのではないでしょうか。
なぜハトは高い場所にくるの?
群れで行動するハトは、仲間意識、縄張り意識がとても強い鳥です。人の多い環境で生活するハトも居れば、人気の少ない場所で生活するハトもいます。
年々増加しているハトにとってのねぐらとなる場所、森林なども減ってしまったことで人工的な高い場所での安心感が飛来増加の要因ではないかと思われます。
餌場を離れたハトがビルやマンションなど、安心できる場所と認識してねぐらや子育ての時期には巣を作ります。
仲間意識があることで、家族を守るための役割を持ち、一度作った巣を撤去しても同じ場所に再び巣を作ろうと戻ってくることがあります。
私たちの生活で糞尿被害や騒音被害で悩まされているご家庭が多くいらっしゃいますが、害鳥被害を起こすのは決してハトだけが悪い訳ではないことを忘れず、ハトにとっても人間にとってもより良い環境づくりとして私たちが対策をしていかなくてはならない問題であると言えます。
日本にいるハトの種類は?
世界では約300種類のハトがいると言われています。日本に生息・繁殖しているハトの種類は「ドバト」「キジバト」「カラスバト」「シラコバト」「アオバト」「キンバト」などです。なかでも増殖が増え続け被害の多くは「ドバト」と「キジバト」です。
ドバト(カワラバト)
上記のように都心を始め、多くの場所で見かけるハトのほとんどはドバト(カワラバト)
警戒心が少なく首筋が緑かかっていて体色は灰色。首を振って歩くのが特徴。
元々日本古来のハトではなく、家畜用として飼育されていたドバトですが一般的に神社や公園などでもよく見かけます。
集団性があり、仲間を増やして飛来するので被害も多く目立ちます。首を振る行動は色々な憶測がありますが、歩行や聴覚などを安定させるためとも言われています。

キジバト(山鳩)
日本都市でも見かけるキジバト(山鳩)は元々山地で生息していましたが、ドバトと同様に人の生活に進出してきています。
キジバトは紫色の体で鱗模様。首筋が灰青色のしま模様。鳴き声が特徴的でこもったようなトーンで「デューデューポッポーポッポー」と繰り返し鳴く。
飼育しているハト小屋なども存在し、近隣からの苦情が多いと言われています。民家周辺の屋敷林や公園の森林、市街地でも見かけます。
ハトの寿命は?
ハトの寿命はおよそ10年とされ寿命の差は住環境と個体の強さで変わります。飼育され長生きなハトもいれば野生で食べる物によって寿命は異なります。

ケガしたハトを見つけたら?
厳しい自然環境で生きている野鳥のハトには外敵がいっぱい。何らかの理由でケガをして弱っていたり、衰弱しているハトを見かけ心苦しい気持ちになるのは当然です。
自然界の中で生きている以上、人が手をだしてはならないという方もいるかと思いますが、保護飼育の期間が長引き野生に戻すことが困難です。
また、ヒナの場合、巣立ちの練習をしていることで親鳥が探します。例え、かわいそうと思っても、むやみに連れて帰ることはしないでください。親鳥が探しに来るまでそのままにしておくことが大切です。
死亡した鳥獣を見つけたら?
公道路で死亡した鳥獣の場合、道路管理者に処理の依頼を行いましょう。
野生の鳥獣の処理については、捨得したり、傷病による鳥獣を保護したあとに死亡した場合、天然記念物などの特別な鳥獣を除き、埋設、焼却などの処置を行ってください。
基本的に傷病鳥獣の救護などは、鳥獣の本来の生態を守るために保護各市町村によって対応してくれる場合もあるので自然環境保全課などにご相談してみるのも良いでしょう。
自宅のハト対策は業者におまかせください
鳩がベランダの手すりなどに頻繁にやってきたり、室外機の裏に巣を作ると、鳴き声による騒音、多くのフン害、健康被害が懸念されます。
業者に依頼すると、追い出しや巣の撤去、フン清掃や殺菌・防ダニ処理、ベランダに防鳥ネットや剣山(スパイク)を設置して侵入を防ぐなどの対策を行っています。高所作業となるため、個人で設置するのは、大変危険です。専門技術で効果的な対策をしたいなら一度、害鳥業者に相談してみましょう。
クジョリアでは、被害が大きくなってしまう前の対策をご提案させて頂いております。現在ハト被害でお困りの方はお気軽にご相談ください。
まずは安心できる無料調査、無料見積もりでご納得頂けるサービスをご案内致します!
まとめ
一般家庭のベランダや屋根、非常階段、ソーラーパネルの隙間、様々な建物の空間に巣を作られる被害で業者にご相談されるケースが増えています。
特に人懐っこい鳩は、餌をもらえると認識すると頻繁にやってきて、可愛らしい印象がありますね。
しかし、人馴れしてしまうとフン害が発生したり、外敵のいない居心地の良い環境を与えてしまうと、フン害や鳴き声による騒音、健康被害など様々な影響をもたらすおそれがあります。
一度棲みついてしまった鳩の群れを追い出すのは困難になってしまうので、鳩等の害鳥をおびき寄せる原因となる餌やり餌付けは絶対にやめましょう。
自宅で鳩被害に困ったら、管理会社もしくは自己負担となるかのどちらかになるので、被害が大きくなる前に、早めの対処をしましょう。
害鳥駆除|千葉・東京・茨城の害鳥駆除・防除・対策専門のQujolia(クジョリア)


.png)